

一通り踊れるようになっていて、休み時間を中心にテストを通して次のステップに挑戦しているところ。あとは、外で隊形移動の確認をすれば完成だ!

外で隊形移動を確認するってけっこう大変……。100人以上の子たちをグラウンドで掌握して混乱せずに確認しきるにはどうしたらいいのかな?
こんな人のための記事です。
10時間扱いで、運動会本番までに「南中ソーラン」を仕上げる今回の単元。残すは隊形移動のみ。7/10時間目は、隊形移動を確認する1時間です。ここからはグラウンドでの活動、そして子どもたちの立ち位置が変わるので、指示をいかに通していくかが大切になってきますよね。
〇この1時間で達成したいこと!
・隊形移動で自分がどこに立ち、どこに移動して踊るのかを理解できる。
〇1時間の展開
〇スムーズに隊形移動を教える工夫
この1時間で達成したいこと!
・隊形移動で自分がどこに立ち、どこに移動して踊るのかを理解できる。
1時間の中で場所を教えきること。
これができれば、この時間は目標達成です。
ただ、100人以上の子どもたちをグラウンドで動かすってけっこう大変なことですよね。
ここには工夫が必要です。私がしている工夫は
①事前に指導
②目印
③移動だけを抽出
④歩く

それでは、具体的な1時間の展開を見ていきましょう!
1時間の展開例
①準備運動
ここでは、『ラジオ体操』で準備運動を行います。
開会式で前に出てラジオ体操をする役割が決まっていれば、その子たちを前に出し、経験を積ませます。できれば、せっかくグラウンドでの練習なので、開会式の立ち位置を確認してその場でやらせたいですね。
②主運動につながる準備運動
隊形移動の確認が主なので省略
③主運動Ⅰ
隊形移動を教えていきます。
教える隊形移動は
1,入場待機場所の確認
2,待機場所から踊り始める場所へ
3,間奏を利用した隊形移動の場所へ
4,最後のポーズの場所へ
5,退場
これを、まずは移動部分だけ抽出して確認していきます。

昔は、もっと複雑な隊形移動を入れていましたね。踊りながら放射になったり、前後入れ替わったり、円になったり。でも、最近は「限られた時数の中でできる範囲の完成度を求める」という流れになっているので、隊形移動は「間奏部分」と「最後のポーズ」のみにしています。
1,入場待機場所の確認
ここで大事になってくるのは、グラウンドでいきなり指示を出して確認するのではなく、事前に各クラスでイメージを共有しておくこと。何よりも、事前の指導がスムーズにこの時間を進めるための肝になります。事前に指示を出しておけば、あとは目印を用意することですぐに動くことができます。
2,待機場所から踊り始める場所へ
ここでは、先生方の事前の確認が大事!
各クラスの先生方に自分のクラスを掌握してもらいます。ここは混乱がないように、移動場所まで歩いていき、場所を確認します。

よくあるのは、隊形移動が指示する先生の頭の中にだけあって、それを各担任が共有できておらずただ見ているだけ。子どもも担任もどうすればよいか分からずオタオタ。そして、指示が伝わらずに指示を出す先生はイライラ。そんな事態にならないように、先生方で事前に確認することが大事ですね。
あとは、自分なりの目印を見つけさせることが大事!
最初は先生が目印を設定して場所を確認させるとしても、本番ではそれがなくなります。
「自分の目で、自分の頭で覚えるんだよ!」ということを徹底していきます。
3,間奏を利用した隊形移動の場所へ
ここも目印を示してあげて、歩いて移動させます。
最近は、より単純な隊形移動、そして保護者にも子どもたちの顔が見えるように……ということで、保護者席向きと児童席向きを単純に入れ替える隊形移動にしています。
具体的な隊形の移動の仕方を確認したい方はこちら!
表現運動『運動会に向けた表現(南中ソーラン)の指導』②~単元に入るその前に…~ | 雄剛先生.com~ヤングYugoへのメッセージ~
4,最後のポーズの場所へ
ここも各担任に協力してもらいます。
クラスごとに「荷上げ」の動きをしながら円形を作っていくので、各担任に中心に立ってもらいます。それを目印として中央に集まる動きを実際にやってみます。
5,退場
これは、退場の動きを示してやらせてみる。
退場門から出て、児童席に戻るが一番シンプルな気がしますね。
④交流
*今回は教えることが主で、交流はなしですね。
⑤主運動Ⅱ(試しの踊り!)
高学年であれば、最後に通して踊らせてみます。
きちんと「自分の目で、自分の頭で判断する!」ができていれば、多少の混乱はあってもできる!
……と信じたいですね。
⑥整理運動
怪我や体調不良がいないかを確認します。
⑦振り返り
今回は、7/10時間目。「隊形移動ののどんなところができて、課題はどこか?」と書く観点を示します。そうすることで、この時間の「思考力・判断力・表現力等」が見えるようにしていきます。
*グラウンドで振り返るのは厳しいので、できれば終了時間より早めに終わって教室で書かせるようにします。
スムーズに隊形移動を教える工夫
私が意識しているのは以下の4点です。
①事前に指導
これに尽きます。子どもも、各担任も、隊形移動のイメージを共有してあること。これができていれば、8割失敗はないと思います。
②目印
今回くらいの隊形移動であればそこまで必要ないかとは思いますが、マーカーやケンステップなどで場所を示し、子どもたちが移動する目安を作っておくと、スムーズに移動できます。そして、移動した先で、自分なりの目印を見つけさせることで、次からは目印を用意する必要がなくなります。

たまに、低学年なんかだと地面に印を付ける子が……。
次に練習する時には消えちゃうよ。
③移動だけを抽出
時間的にも、子どもの集中力的にも、いきなり踊りとセットで教えるのは厳しいですね。
必ず隊形移動のみに絞って、まずは確認をします。
④歩く
最初は混乱を防ぐためにも、歩いた方がいいですね。
「表現運動『運動会に向けた表現(南中ソーラン)の指導』⑨ ~7/10時間目【6年5月】」のまとめ
それでは、まとめです。
〇この1時間で達成したいこと!
・隊形移動で自分がどこに立ち、どこに移動して踊るのかを理解できる。
〇1時間の展開
〇スムーズに隊形移動を教える工夫
いかがだったでしょうか?本番まで残り3時間。あとは、隊形移動をスムーズにできるようにすること、法被を着た踊り方の確認、リハーサルでおしまいです。完成間近ですね。ここまでくると、あとは子どもたちのモチベーションをどう上げていくかという所が大事になってきますね。
もし「こんなやり方もあるよ!」「このやり方が効果的だった!」というアイデアがあれば是非教えてください。一緒に学んでいけたら嬉しいです!
私の初書籍が2025年8月29日に発売予定です。ぜひ読んでもらえると嬉しいです!
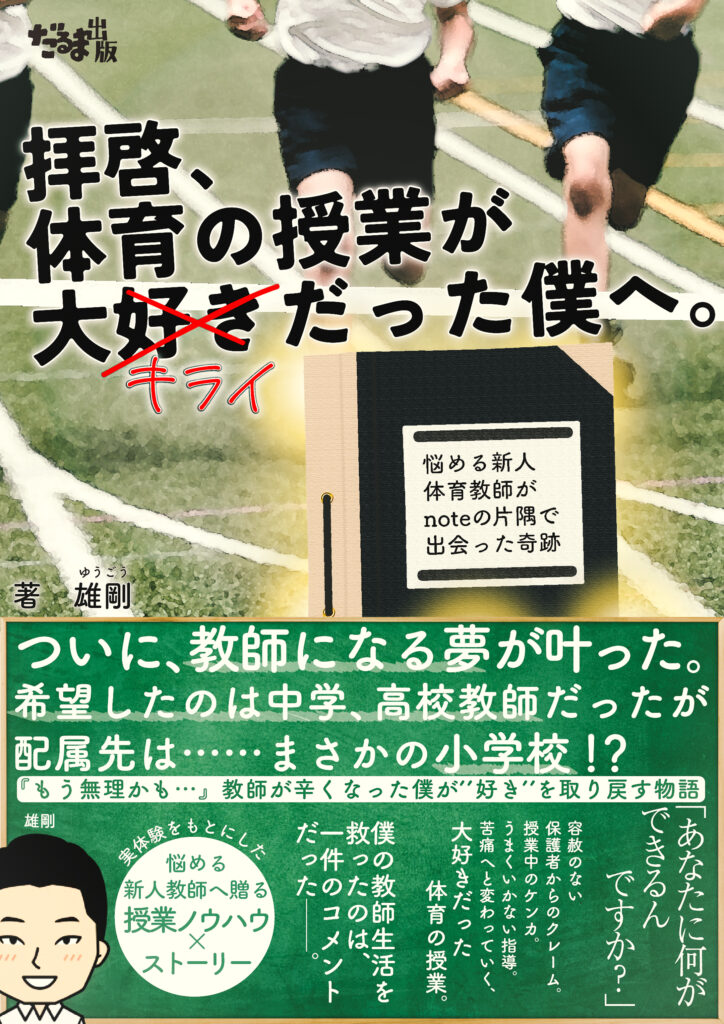
にほんブログ村

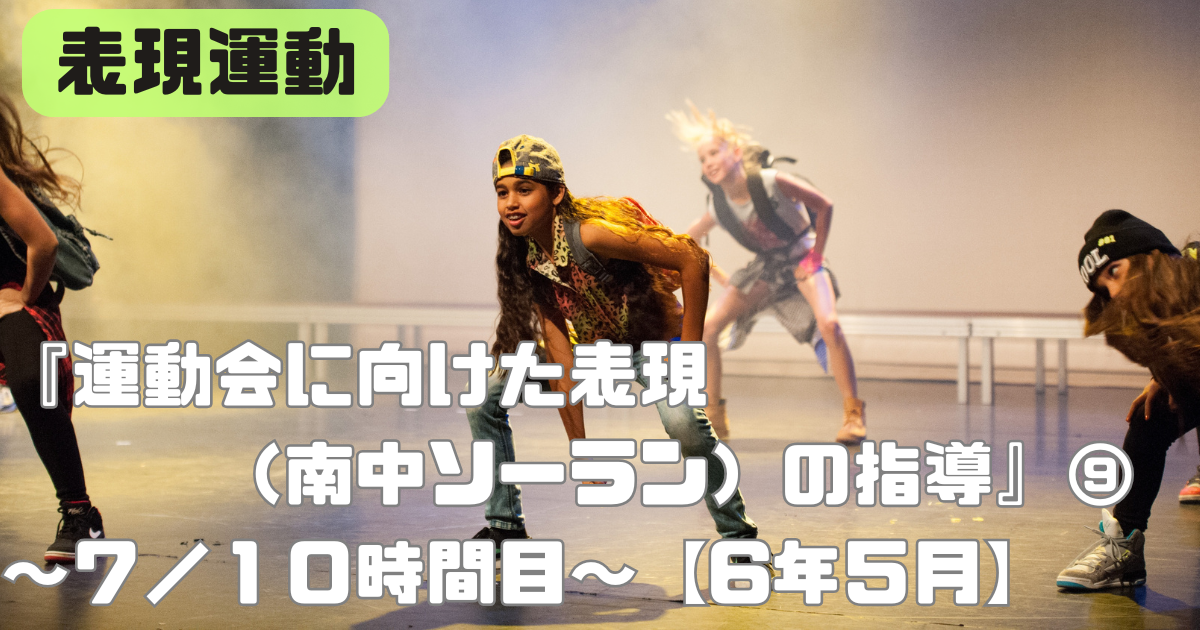


コメント